青木英剛氏×オートデスク株式会社 加藤久喜氏 スペシャルトーク
多様な社会課題にも貢献する宇宙ビジネスでは
設計・ものづくり双方の日本の高度な技術力に
大きな期待が寄せられている

〈パネリスト〉
青木英剛氏(写真中央)
宇宙エバンジェリスト
一般社団法人 Space Port J端pan 創業理事
加藤久喜氏(写真右端)
オートデスク株式会社 技術営業本部長
〈モデレーター〉
小西貴裕(写真左端)
応用技術株式会社 代表取締役専務
身近なものになろうとする宇宙ビジネス。宇宙エバンジェリストとして世界を飛び回る青木英剛氏の基調講演を受け、青木氏とオートデスク株式会社の加藤久喜氏にご参加いただいたトークセッションの話題は、エンジニア視点での宇宙開発の難しさから宇宙ビジネスの現状と今後の展望、さらには宇宙ビジネスにおける当社の可能性まで、さまざまな領域に及びました。そのセッションの模様をダイジェストでお伝えします。
地上では動作検証できない。それが宇宙船設計の最大の難しさ
小西「青木さん、本日は刺激的なご講演をありがとうございました。興奮冷めやらぬところとは思いますが、まずはオートデスクの加藤さんに今日の講演の感想をうかがいたいと思います。」
加藤氏「宇宙がこれほど身近なものになっていることにまず驚かされたというのが正直なところです。青木さんにお聞きしたいことは本当に多いのですが、ぜひ伺いたいのは、エンジニアとしての宇宙開発の難しさです。宇宙船の場合、地上で動作検証するわけにはいきませんよね。そうなるとシミュレーションの役割が一般的な工業製品の比ではなく重要になると思うのですが。」
青木氏「ご指摘の通り、無重力空間を含めた宇宙環境の検証を地上で行うことはできません。エンジニアにとっては、真空状態の熱伝導や電波の伝わり方など地上でも検証可能な要素を加味し、いかに高精度なシミュレーションを行うかというのがやはり一番の難しさになると思います。無重力空間の熱膨張などの関係でドッキング時にボルトサイズが合わなかったという事例も実際にあり、開発者は最後まで気が抜けないというのが正直なところです。宇宙船や衛星の開発では、宇宙空間のシミュレーションの精度向上はとても重要な課題になると思います。」
小西「そうすると宇宙ビジネスの観点では、宇宙空間のシミュレーションというような分野もチャンスになり得るわけですね。」
青木氏「まさにその通りです。私が現役の設計者だった頃は、夜にシミュレーションツールを走らせて帰宅し、朝出社してみるとパソコンがフリーズしていたということも日常茶飯事でしたが、今は即座に結果が返ってきますからその進化は隔世の感がありますね。」
衛星向けの信号機サービスなど新たなビジネスが次々に台頭
小西「私が驚いたのは、イーロン·マスク氏のスペースX社だけでも5000機に及ぶ衛星がすでに宇宙を飛んでいるという事実でした。素人めいた質問になってしまいますが、地上で言う交通事故のようなものは起きないのでしょうか?」

青木氏「宇宙には現在、1~2万機の衛星が飛び、退役した衛星の残骸や宇宙飛行士が落としたレンチやボルトまで含めれば、数万の物体が宇宙に浮かんでいます。衝突すれば宇宙デブリの数はさらに増えるわけですから、確かに大問題です。でも宇宙よりはるかに狭い地上に何億、十数億という車が走り回っていることを考えると、数万というのは取るに足らない規模と言えます。ですから、まだその心配はないのでご安心くださいというのがその答えです。実は衛星航路をシミュレーションし、衝突を回避する”信号機サービス”を提供するベンチャーもすでに現れています。こうしたサービスを利用することで、衛星の安全な運用は今後も保たれるはずです。」
小西「なるほど。私のような素人が感じた疑問も実は宇宙ビジネスの種になり得たわけですね。」
青木氏「まさにその通りです。講演でもお話ししした通り、私は日本を代表する大企業からものづくり企業まで、さまざまな企業の宇宙ビジネスをコンサルティングしていますが、その経験からも宇宙ビジネスと無関係な企業を探す方が難しいのではないでしょうか。もちろん、宇宙という未経験の領域への進出が難しいのは当たり前のことです。しかし、外部の視点で各社のアセットを洗い出し、『御社のこの技術は、宇宙のこの領域に生かせそうですよ。』と指摘することで、各社の技術者たちがビジネス化に向け一気に動き始めたという事例もすでに数多く存在しています。」
小西「ところでオートデスクさんと宇宙の関わりは現在どんな状況にありますか?」

加藤氏「現CEOのアンドリュー·アナグノストが、スタンフォード大学で博士号を取得し、NASAエイムス研究センターで宇宙開発に携わったエンジニアとしての経歴を持つこともあり、宇宙との関係はすでにかなり近しいと思います。NASAとの協業によるジェネレーティブデザイン技術を利用した火星着陸機のコンセプトデザインはその一例で、国内では、インターステラテクノロジズ社も当社のユーザーです。また当社は毎年能代市で行われる宇宙イベントを支援し、宇宙開発に関する優れた設計を行う学生グループにAutodesk賞を授与していますが、受賞作が実際の宇宙開発に採用される事例も登場しています。」
宇宙ビジネスにおける日本企業の役割は極めて大きい
小西「青木さんにお聞きしたいのですが、宇宙ビジネスにおける日本企業のポテンシャルをどうご覧になりますか?」

青木氏「設計·製造の双方で高度な技術力を備える日本のような国は、世界を見渡してもそう多くありません。例えば世界5位の経済大国に成長したインドでは、日本より前に月面着陸に成功するなど宇宙開発も盛んですが、高度な板金技術や溶接技術を持つ人材は今も圧倒的に不足しているのが実情です。日本の町工場をインドに誘致するプロジェクトが水面下で進んでいる背景には、こうした事情があります。シリコンバレーを擁するアメリカでも事情は同じで、リアルなものづくり人材はやはり不足しています。米中関係の緊張化に伴い、中国にものづくりを依存することが難しくなる中、日本のものづくり企業にとって、宇宙が大きなビジネスチャンスになることは間違いないと考えています。」
小西「基調講演で私が驚かされたのは、宇宙からの覗き見がすでに進んでいるというお話でした。実際のところ、そうしたデータは誰でも入手可能なのですか?」
青木氏「以前であれば衛星写真の入手に関する制約は大きかったのですが、世界中のベンチャー企業が衛星を飛ばす今は誰でも入手することが可能です。そうした企業のサイトにアクセスし、この日時のこの場所の写真が欲しいと指定し、クレジットカードで決済を済ませれば簡単に入手できますし、写真を解析し、必要なデータをクライアントに提供するサービスも成長しています。ただし講演でも触れたように、衛星写真という宇宙ビッグデータを競合企業やサプライチェーンの分析に利用していることをあえて明言する企業は存在しません。同様の取り組みを行う企業は、すでにかなりの数に及んでいるのではないでしょうか。」

小西「宇宙ビッグデータ活用は防災·減災の観点でも興味深いものがあります。というのも当社は以前から、国交省様や自治体様に地形データなどに基づく災害シミュレーションサービスを提供しているのですが、肝心のデータのメンテナンスが+分に行われていないことが大きな制約になっていることを強く感じてきました。衛星による最新データを利用することで、より高精度な分析結果を、より広い範囲方々に提供できるようになるはずです。」
青木氏「日本に限らず、災害対策は起きた後に行うんですよね。しかし宇宙ビッグデータを分析し、適切な対応を継続的に行うことで、災害発生時に迅速に対応できるだけでなくトータルコスト削減も可能になります。私は機会あるごとに政府や自治体の方々にこうしたお話をさせていただいているのですが、応用技術さんも含め、今日お集りの皆さんにもぜひ声を上げていただきたいと思っています。」
小西「国内通信キャリアの一部で、すでに衛星経由の通信経路が採用されているというお話も興味深くお聞きしました。当社は”誰もがBIMにつながる世界へ”をテーマにBIM/CIM活用を支援していますが、建設現場でデータを活用しようとする場合、通信環境が大きな課題になることが少なくありません。衛星インターネットはその解決策として大いに期待できそうですね。」
青木氏「その通りです。従来は特に山間部の工事現場のネットワーク構築には多大なコストが生じていたと思いますが、宇宙インターネットでは月数万円のコストで4G、5Gと同水準の通信帯域を確保することが可能です。」
小西「オートデスクさんは以前からクラウド経由のデータ共有を積極的に推進しています。サービス強化に向け、宇宙インターネット活用などもすでに検討されていたりするのでしょうか?」
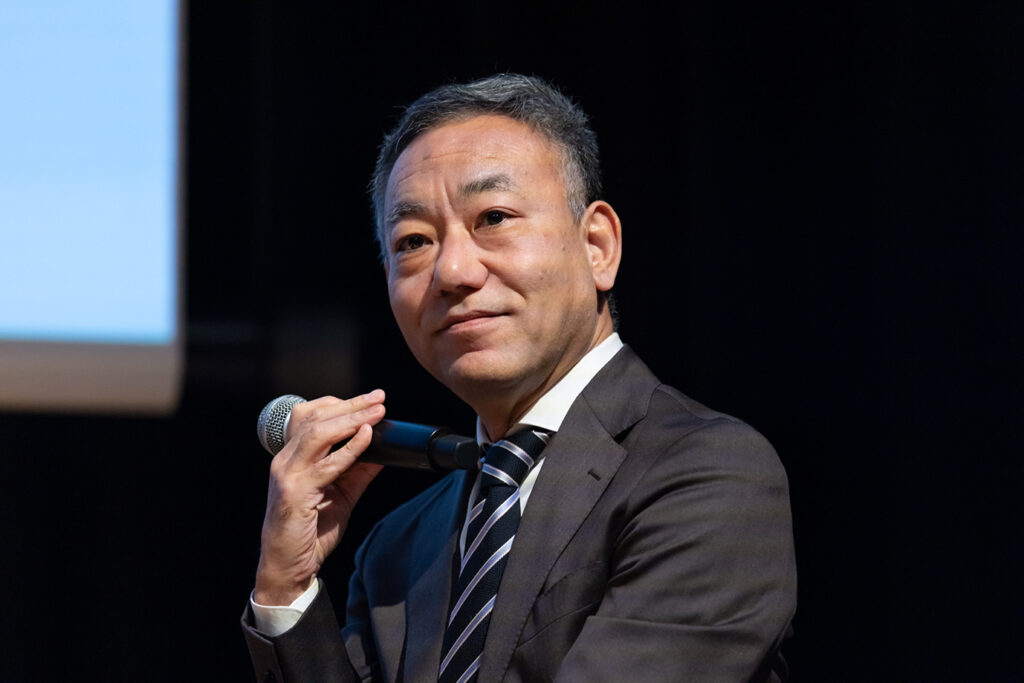
加藤氏「現時点では、宇宙インターネットに関連する具体的な計画はありません。建設現場におけるデジタルデータ活用という観点では、デジタルツインの推進を強く意識しています。土木インフラの中に建築物があり、建築物の中に工業製品があるという関係性を考えると、土木·建築·製造はそれぞれ切り離して考えるべきものではないはずです。クラウドプラットフォーム上へのCADデータ統合により、土木·建築·製造をデジタルツインとして統合し、建設現場に提供していくことも可能になると考えています。その実現には、通信環境の確保やセキュリティなど乗り越えるべき課題があることは間違いありませんが、宇宙インターネットはこうした課題解決に大きな役割を果たすことが期待できそうですね。」
では宇宙ビジネスにおいて、私たちはどの道を進むべきなのか?
小西「衛星利用に関するお話をお聞きしていると、今後は自社で衛星を持つというのも一つの選択肢になりそうですね。」

青木氏「それも十分あり得ます。”マイ衛星”という言葉がある通り、自社サービス専用衛星を持つ企業もすでに現れています。一例がウェザーニュースさんで、北極海航路の航行情報提供に関するサービスに保有する2機の衛星の情報をフル活用しています。珍しい例では福井県も自治体として衛星を保有し、県内の森林管理に役立てているところです。ただし、1機だけでは効果は限定的です。そのため高級コンドミニアムのように複数企業が衛星を共有するサービスもすでに登場しています。」
小西「先ほど青木さんは、宇宙ビジネスのコンサルティングはそのアセットを見ることから始めると話されました。唐突なお願いになってしまいますが、青木さんの目に私たち応用技術がどう映ったかお聞かせいただけると嬉しいのですが。」
青木氏「そうですね。先ほどもお話しした通り、宇宙の無重力空間のシミュレーションは宇宙開発の大きな課題ですが、それに加え、いわゆるリバースエンジニアリングの難しさもその特徴の一つです。たいていの工業製品はそれを入手して学ぶことができますが、ロケットや衛星は、打ち上げてしまえば触れることができません。こうした中、高精度な無重力空間のシミュレーションや衛星がモジュールの組み合わせで開発できる仕組みの提供は、御社の成長だけでなく、宇宙の民主化という観点でも大きな意味を持つと思います。」
小西「ありがとうございます。青木さんの基調講演をお聞きして、宇宙ビジネスの可能性のようなものを実感された方も多いと思います。最後に今日お集りいただいた皆様へのメッセージをいただけますでしょうか。」
青木氏「講演において私は30年前のインターネット勃興期と現在の宇宙ビジネスの類似性を指摘しました。インターネットが私たちの社会に欠かすことができないものになったのと同じように、遠からぬ未来には宇宙ピジネスも欠かすことができない存在になると私は考えています。今日の私のお話が皆様の宇宙という新たなビジネス領域の可能性を考えるきっかけになることを大いに期待しています。」
